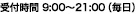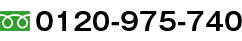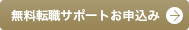HOME > ドライブワーク通信 > トラックドライバーの過労死の事例と、事業者が行うべき対策を紹介
ドライブワーク通信
トラックドライバーの過労死の事例と、事業者が行うべき対策を紹介
厚生労働省は、毎年11月を「過労死等防止啓発月間」と位置づけ、過労死をなくすための取り組みを行っています。そこで本記事では、トラックドライバーの過労死の事例や、過労死防止の具体的な対策などについて紹介していきます。

トラックドライバーの過労死は、どのような形で起こり得るのでしょうか。実際にあったケースを幾つか紹介します。
過労死ラインを大幅に超過していたケース2018年、大阪府の運送会社である「田平陸送」に勤めていた長距離トラックドライバーの男性(当時52歳)が、運転中に心筋梗塞を発症し、搬送先の病院で死亡した事例です。運行記録などから、この男性の直近半年間の時間外労働が月あたり平均159時間と、過労死ラインである月平均80時間を大幅に超過していたことが分かり、労災と認定されました。
休日に亡くなったものの労災が認められたケース2019年、引っ越し大手「アートコーポレーション」の子会社、「アートバンライン」に勤めていた長距離トラックドライバーの男性(当時53歳)が自宅で急死しました。休日に自宅で亡くなったケースですが、遺族が労災を申請。労基署の調べにより、亡くなる前の半年間の時間外労働時間が月あたり65~110時間だったことが分かり、労災が認められました。
労働者性が争点となっているケース2013年、埼玉県の運送会社「東京デリバリーセンター」のトラックドライバーとして働いていた男性(当時62歳)が、急性虚血性心疾患により亡くなりました。亡くなる直前6ヶ月の時間外労働時間は月平均80時間の過労死ラインを上回っており、労災と認められました。その後、2024年に遺族が会社に対し、過重労働を防ぐ安全配慮義務を怠ったとして、会社を提訴しました。一方の会社は、亡くなった男性が独立した事業主であるとし「労働者性はない」と主張しています。
トラックドライバーの過労死対策は、ドライバー本人に任せるのではなく、雇用主である事業者が主体的に取り組む必要があります。
ドライバーの命はここで述べるまでもなく大切なものですが、過労死が発生したという事実は、会社の評判にも大きく影響します。また、運転中の過労死は、重大な事故を引き起こす可能性もあります。
国土交通省の「トラック輸送の過労運転防止対策マニュアル」では、トラックドライバーの過労運転を防ぐための対策として、以下の9点が紹介されています。
- 1. 事業者が一丸となって、トップから過労運転を防ぐ
- 2. 過労のメカニズムを理解し、睡眠を改善する
- 3. 点呼を活かして過労運転を防止する
- 4. 余裕のある運行計画を作成し、その後も運行支援をすすめる
- 5. 健康管理を日常化する
- 6. 運転者が相談しやすい職場環境をつくる
- 7. 荷主・元請事業者に理解してもらう
- 8. 最新技術を駆使して、安全対策に取組む
- 9. 積極的に休憩施設を利用する
厚生労働省は、毎年11月を「過労死等防止啓発月間」と位置づけ、過労死をなくすための取り組みを実施しています。
トラックドライバーは長時間労働が慢性的な課題となっており、実際に過労死が発生してしまった事例を見ても、過労死ライン(月80時間以上の時間外労働)を超えるケースが多くなっています。
また、トラックドライバーの過労死は、その業務の性質上、運転中に発生するリスクもあり、周囲を巻き込んだ事故にも発展しかねません。ドライバー個人に対策を委ねるのではなく、事業者側が責任を持って、主体的に対策を行うことが求められます。
-
白トラ行為への規制強化 ポイントを解説
2026年4月1日より、貨物自動車運送事業法の改正法が一部施行され、違法な白ナンバートラック(白トラ)への規制が強化されます。従来の白トラ規制は、主に運送を行った事業者が処罰の対象でしたが、この規制強化により、運送を行った荷主も責任を問われることになります。 -
冬用タイヤは「溝深さ」に注意 重要性と確認方法を紹介
冬季のトラック輸送では、路面の凍結や積雪がある地域での走行が避けられず、冬用タイヤの装着が不可欠です。しかし、安全に走行するためには、単に冬用タイヤを履くだけでは不十分で、適切な管理が欠かせません。なかでも特に重要なのが、タイヤの「溝深さ」です。本記事では、大型車の冬用タイヤにおける溝深さの基礎知識や重要性、点検方法などを分かりやすく解説します。ぜひ参考にしてください。 -
1月開催!外国籍ドライバー採用に向けたネパール視察ツアー企画!
2024年3月、特定技能制度に追加された自動車運送業分野。弊社アズスタッフでは先行して特定技能ドライバーの教育事業をネパールにて展開し、依頼に対して迅速な対応ができるように、準備を進めてきました。現在は教育を終えて内定を待っている候補者が多くいるため、圧倒的なスピード感での入国を実現させることが可能となります。ネパール現地では国家資格を有する日本人の教職員を駐在させ、ドライバー教育を行っております。そして今回、1月21日(水)~23日(金)にかけ実際の教育現場の見学や、現地の日本語学校、教習所を視察し面接が可能なツアーを開催することが決定いたしました。今回はその内容についてご紹介します。 -
現地教育
弊社アズスタッフでは、ネパールの現地企業と連携した特定技能ドライバー教育事業の開始を発表しました。2024年3月、特定技能制度に自動車運送業に追加されましたが、現状はまだ広く浸透していないことを背景に、アズスタッフでは、国家資格を有する日本人の教職員を現地に駐在させ、ドライバー教育を行う事業に乗り出しました。今回はその現地での事業の内容をご紹介します。 -
ヨシ! 「仕事猫」が車輪脱輪事故防止を啓発
一般社団法人日本自動車工業会は、人気キャラクター「仕事猫」とコラボし、大型車の車輪脱落事故防止を啓発するチラシを制作しました。本記事では、車輪脱落事故の概要や原因、日常的に行える対策などを紹介していきます。「仕事猫」や、「車輪脱落予兆検知装置」についても解説していくので、ぜひ参考にしてください。