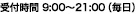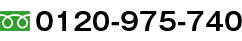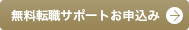HOME > ドライブワーク通信 > 事故防止に役立つヒヤリ・ハット映像
ドライブワーク通信
事故防止に役立つヒヤリ・ハット映像
トラック事故の実に9割が、免許取得から10年以上経ったベテランドライバーによって起きていることをご存知ですか?
運転に慣れたドライバーこそ、事故の危険性は常に心に留めておきたいものです。
全日本トラック協会のWEBサイトでは、会員事業者から提供されたドライアブレコーダーの映像をもとに作成したヒヤリ・ハット映像を視聴することができます。定期的にチェックし、適度な緊張感を持って運転に臨むと良いでしょう。
ヒヤリ・ハットとは、結果的に重大事故にはならなかったものの、その一歩手前の、危険な事例のことです。ヒヤリ・ハットの事例を共有することで、普段の業務に潜む危険を再認識し、危機意識を高めることで、事故を未然に防止する効果があります。
事例1:駐車車両の多い細い路地
https://www.jta-hiyari.jp/movie/?id=00001
駐車車両の多い道を走行中のヒヤリ・ハットです。交通量や人通りは少なく、一見すると危険な道には見えませんが、実は駐車車両による死角が多く、注意が必要です。映像では、車の陰から飛び出してくる子どもと危うく接触するところでした。
事例2:住宅街の交差点
https://www.jta-hiyari.jp/movie/?id=00043
交差点でのヒヤリ・ハットです。映像では自転車の方が「止まれ」の表示を無視して飛び出してきました。ルールに違反しているのは自転車の側ですが、仮に接触事故になっていた場合、どうしてもトラックのほうが加害者になってしまいます。周囲のひとが交通ルールを破ることもあると念頭に入れ、注意を心掛けましょう。
事例3:夜間の交差点
https://www.jta-hiyari.jp/movie/?id=00035
夜間のヒヤリ・ハットです。無灯火の自転車が車道に出てきたため、気付かなければ接触していたかもしれませんでした。こちらもルールを破っているのは自転車の方ですが、相手の違反でこちらが加害者になりかねなかったという事例です。
事例4:コンビニ駐車場
https://www.jta-hiyari.jp/movie/?id=00009
コンビニ駐車場でのヒヤリ・ハット。方向転換の際、脇の死角から飛び出すようにして追い抜いてきた乗用車に、接触する危険がありました。方向転換を行う場合は、周囲への確認をよりいっそう入念に行う必要があります。
事例5:狭い路地
https://www.jta-hiyari.jp/movie/?id=00016
人通りが少なく、狭い路地を走行中、路端に駐車して荷役作業を行っていた別のトラックから、荷物が倒れ込んできたというヒヤリ・ハットです。閑静な通りであってもスピードを出しすぎず、周囲に注意を配ることで、不測の事態にも事故を防ぐことができます。
事例6:郊外路のカーブ
https://www.jta-hiyari.jp/movie/?id=00010
郊外路のカーブで起きたヒヤリ・ハットです。このように見通しの良い道では、ついスピードを出しすぎてしまうドライバーも少なくありませんが、映像ではカーブで膨らんできた対向車とあわや衝突するところでした。
事例7:見通しの悪いカーブ
https://www.jta-hiyari.jp/movie/?id=00004
見通しの悪いカーブでのヒヤリ・ハットです。カーブを抜けた先では渋滞が起こっており、もしもう少しスピードが出ていたら追突して玉突き事故が起きていたかもしれません。
文/BUY THE WAY lnc.
-
白トラ行為への規制強化 ポイントを解説
2026年4月1日より、貨物自動車運送事業法の改正法が一部施行され、違法な白ナンバートラック(白トラ)への規制が強化されます。従来の白トラ規制は、主に運送を行った事業者が処罰の対象でしたが、この規制強化により、運送を行った荷主も責任を問われることになります。 -
冬用タイヤは「溝深さ」に注意 重要性と確認方法を紹介
冬季のトラック輸送では、路面の凍結や積雪がある地域での走行が避けられず、冬用タイヤの装着が不可欠です。しかし、安全に走行するためには、単に冬用タイヤを履くだけでは不十分で、適切な管理が欠かせません。なかでも特に重要なのが、タイヤの「溝深さ」です。本記事では、大型車の冬用タイヤにおける溝深さの基礎知識や重要性、点検方法などを分かりやすく解説します。ぜひ参考にしてください。 -
1月開催!外国籍ドライバー採用に向けたネパール視察ツアー企画!
2024年3月、特定技能制度に追加された自動車運送業分野。弊社アズスタッフでは先行して特定技能ドライバーの教育事業をネパールにて展開し、依頼に対して迅速な対応ができるように、準備を進めてきました。現在は教育を終えて内定を待っている候補者が多くいるため、圧倒的なスピード感での入国を実現させることが可能となります。ネパール現地では国家資格を有する日本人の教職員を駐在させ、ドライバー教育を行っております。そして今回、1月21日(水)~23日(金)にかけ実際の教育現場の見学や、現地の日本語学校、教習所を視察し面接が可能なツアーを開催することが決定いたしました。今回はその内容についてご紹介します。 -
現地教育
弊社アズスタッフでは、ネパールの現地企業と連携した特定技能ドライバー教育事業の開始を発表しました。2024年3月、特定技能制度に自動車運送業に追加されましたが、現状はまだ広く浸透していないことを背景に、アズスタッフでは、国家資格を有する日本人の教職員を現地に駐在させ、ドライバー教育を行う事業に乗り出しました。今回はその現地での事業の内容をご紹介します。 -
ヨシ! 「仕事猫」が車輪脱輪事故防止を啓発
一般社団法人日本自動車工業会は、人気キャラクター「仕事猫」とコラボし、大型車の車輪脱落事故防止を啓発するチラシを制作しました。本記事では、車輪脱落事故の概要や原因、日常的に行える対策などを紹介していきます。「仕事猫」や、「車輪脱落予兆検知装置」についても解説していくので、ぜひ参考にしてください。