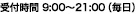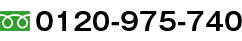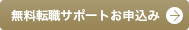HOME > ドライブワーク通信 > 業務車両の必須装備。ドライブレコーダーのメリットとは?
ドライブワーク通信
業務車両の必須装備。ドライブレコーダーのメリットとは?
近年シェアが高まっているドライブレコーダー。特に業務車両にとっては必須装備といえます。
本記事では、そんなドライブレコーダーの役割や搭載するメリットについて、改めてご紹介していきます。
ドライブレコーダーとは、車内・車外の映像や音声、速度、GPSなど、運転中の様々な情報を記録しておくことのできる車載機器です。
日本では2000年代に実用化が始まり、現在はタクシーやバス、トラックなどの業務車両を中心に普及が進んでいます。全日本トラック業界が実施した調査結果によると、トラック事業者では平成26年の時点で、7割以上の車両に導入されています。
交通事故を自分ひとりの努力でゼロにすることはできません。どんなに注意深く運転を行っても、たまたま傍を通りがかった相手の不注意ひとつで、事故の当事者になってしまう可能性があります。
そしていざ事故が起こった時、客観的な記録なしに、どちらに落ち度があったのかを救命することは非常に困難です。信号は青だったのか?強引な割り込みや、危険な煽り運転はなかったのか?当事者同士の証言をもとに究明しようにも、双方の言い分が食い違ってしまうことが少なくないためです。
特にバスやトラックの場合は、車体が大きい分、「落ち度がない」という確かな証拠がなければ、重い責任を背負わされがちです。このことを利用し、悪意を持って法外な示談金や損害賠償を請求する「当たり屋」行為を行う人も残念ながら後を絶ちません。
ですがドライブレコーダーを搭載していれば、もしも事故の当事者になっても、すばやく正確に原因究明を行うことができ、「落ち度がないにもかかわらず責任を負わされる」などのトラブルを防ぐことができます。また車上荒らしの原因究明や、警察による誤認検挙の防止にも役立ちます。きちんと記録を残しておくことが、ドライバー自身の身を守ることにも繋がるのです。
・若手ドライバーの安全教育に役立つ
全日本トラック協会が推奨する「運行管理連携型」のドライブレコーダーでは、あわや大事故に繋がりかねなかった映像を「ヒヤリ・ハット映像」として記録し、若手ドライバーの安全教育に活用することが出来ます。運送業界全体の意識向上に貢献することができます。
・自動車保険の割引を受けられる
損保ジャパンなど幾つかの保険会社は、車にドライブレコーダーを設置した加入者に対して、保険料の割引を実施しています。ドライブレコーダーの導入にはコストがかかりますが、落ち度がない事故で損害賠償を請求されるリスクや、月々の保険料まで含めて考えれば、経済面でも導入のメリットがあります。
全日本トラック協会が実施した調査によると、ドライブレコーダーを導入した事業者全体のうち、実際の事故処理に役立ったと回答した事業者は約4割。安全指導に役立ったという回答は6割ありました。
また7割以上が「運転者の安全意識が高まり、危険運転が減少した」と回答しています。運転中の情報を記録されているという自覚が、運転する上で適切な緊張感をドライバー自身にもたらしていることがわかります。
全日本トラック業界では、ドライブレコーダーの導入促進助成事業を実施しています。
助成の対象となるのは運行管理連携型のドライブレコーダー。ただし東京トラック協会など、一部のトラック協会では、運行管理連携型以外のドライブレコーダーも助成の対象にしている場合もあります。
文/BUY THE WAY lnc.
-
白トラ行為への規制強化 ポイントを解説
2026年4月1日より、貨物自動車運送事業法の改正法が一部施行され、違法な白ナンバートラック(白トラ)への規制が強化されます。従来の白トラ規制は、主に運送を行った事業者が処罰の対象でしたが、この規制強化により、運送を行った荷主も責任を問われることになります。 -
冬用タイヤは「溝深さ」に注意 重要性と確認方法を紹介
冬季のトラック輸送では、路面の凍結や積雪がある地域での走行が避けられず、冬用タイヤの装着が不可欠です。しかし、安全に走行するためには、単に冬用タイヤを履くだけでは不十分で、適切な管理が欠かせません。なかでも特に重要なのが、タイヤの「溝深さ」です。本記事では、大型車の冬用タイヤにおける溝深さの基礎知識や重要性、点検方法などを分かりやすく解説します。ぜひ参考にしてください。 -
1月開催!外国籍ドライバー採用に向けたネパール視察ツアー企画!
2024年3月、特定技能制度に追加された自動車運送業分野。弊社アズスタッフでは先行して特定技能ドライバーの教育事業をネパールにて展開し、依頼に対して迅速な対応ができるように、準備を進めてきました。現在は教育を終えて内定を待っている候補者が多くいるため、圧倒的なスピード感での入国を実現させることが可能となります。ネパール現地では国家資格を有する日本人の教職員を駐在させ、ドライバー教育を行っております。そして今回、1月21日(水)~23日(金)にかけ実際の教育現場の見学や、現地の日本語学校、教習所を視察し面接が可能なツアーを開催することが決定いたしました。今回はその内容についてご紹介します。 -
現地教育
弊社アズスタッフでは、ネパールの現地企業と連携した特定技能ドライバー教育事業の開始を発表しました。2024年3月、特定技能制度に自動車運送業に追加されましたが、現状はまだ広く浸透していないことを背景に、アズスタッフでは、国家資格を有する日本人の教職員を現地に駐在させ、ドライバー教育を行う事業に乗り出しました。今回はその現地での事業の内容をご紹介します。 -
ヨシ! 「仕事猫」が車輪脱輪事故防止を啓発
一般社団法人日本自動車工業会は、人気キャラクター「仕事猫」とコラボし、大型車の車輪脱落事故防止を啓発するチラシを制作しました。本記事では、車輪脱落事故の概要や原因、日常的に行える対策などを紹介していきます。「仕事猫」や、「車輪脱落予兆検知装置」についても解説していくので、ぜひ参考にしてください。