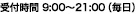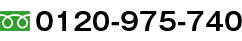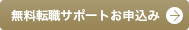HOME > ドライブワーク通信 > 事故防止対策支援推進事業に係る補助金の申請がスタート
ドライブワーク通信
事故防止対策支援推進事業に係る補助金の申請がスタート
2024年7月30日、国土交通省は、事故防止対策支援推進事業にかかわる補助金の申請受付を開始しました。
この補助金は、自動車運送事業における交通事故を防止する目的で実施されるものです。先進安全自動車(ASV)や、運行管理の高度化に活用できる機器の導入する運送事業者に対し、補助を行います。

今回実施される補助事業は、以下の2種類です。
- ● 自動車運送事業の安全総合対策事業及
- ● 先進安全自動車の整備環境の確保事業
それぞれ見ていきましょう。
自動車運送事業の安全総合対策事業及自動車運送事業の安全総合対策事業としては、以下の4つの補助を実施します。
- ● 先進安全自動車(ASV)の導入に対する支援
- ● 運行管理の高度化に対する支援過労運転防止のための支援
- ● 先進的な取り組みに対する支援社内安全教育の実施に対する支援
- ● 社内安全教育の実施に対する支援
また、対象となる事業者は以下に該当する中小事業者です。
- ● 一般乗合旅客自動車運送事業者
- ● 一般貸切旅客自動車運送事業者
- ● 特定旅客自動車運送事業者
- ● 特定旅客自動車運送事業者
- ● 一般貨物自動車運送事業者
- ● 特定貨物自動車運送事業者
なお「社内安全教育の実施に対する支援」を除く3つについては、上記の事業者に事業用車両を貸し出すリース事業者も助成の対象となります。
先進安全自動車(ASV)の導入に対する支援先進安全自動車(ASV)の導入を支援することで、普及を促進し、交通事故の削減を図るための補助です。
運行管理の高度化に対する支援過労運転防止のための支援デジタル式運行記録計(デジタコ)や、映像記録型ドライブレコーダーなど、運行管理の高度化に貢献する機器の導入を補助することで、適切な運行管理や、ドライバーに対する安全指導の向上を図ります。
先進的な取り組みに対する支援社内安全教育の実施に対する支援リアルタイムでドライバーの疲労状態を確認したり、注意喚起ができるようにするための先進機器の導入を補助します。ドライバーの過労を防ぐことで、事故の防止にもつながります。
社内安全教育の実施に対する支援外部機関によるコンサルティングによる、社内の安全教育の費用を補助します。
先進安全自動車の整備環境の確保事業に対する支援先進安全自動車の整備環境の確保事業に対する支援では、スキャンツールの導入費用を補助します。スキャンツールとは、電子制御を用いた省エネ性能の維持に必要なツールです。整備事業者の整備環境を確保し、先進安全自動車の性能を維持することを目的としています。
ここまでに紹介した補助事業は、いずれも受付期間が以下のように定められています。
- ● 2024年7月30日~2025年1月31日
ただし、いずれの補助事業も先着順となっています。補助金の総額が上限に達した場合、上記の期間内であっても受付が終了します。補助を希望する場合は、できるだけ早めに申し込む必要があります。
また、申請する際の窓口は運輸支局などではなく、TOPPAN株式会社となります。
2024年7月から始まった、事故防止対策支援推進事業に係る補助金について解説しました。いずれも補助を受けながら安全対策を行える事業ですが、受付期間内であっても、補助金の総額が上限に達し次第終了となってしまう点に留意しましょう。
-
白トラ行為への規制強化 ポイントを解説
2026年4月1日より、貨物自動車運送事業法の改正法が一部施行され、違法な白ナンバートラック(白トラ)への規制が強化されます。従来の白トラ規制は、主に運送を行った事業者が処罰の対象でしたが、この規制強化により、運送を行った荷主も責任を問われることになります。 -
冬用タイヤは「溝深さ」に注意 重要性と確認方法を紹介
冬季のトラック輸送では、路面の凍結や積雪がある地域での走行が避けられず、冬用タイヤの装着が不可欠です。しかし、安全に走行するためには、単に冬用タイヤを履くだけでは不十分で、適切な管理が欠かせません。なかでも特に重要なのが、タイヤの「溝深さ」です。本記事では、大型車の冬用タイヤにおける溝深さの基礎知識や重要性、点検方法などを分かりやすく解説します。ぜひ参考にしてください。 -
1月開催!外国籍ドライバー採用に向けたネパール視察ツアー企画!
2024年3月、特定技能制度に追加された自動車運送業分野。弊社アズスタッフでは先行して特定技能ドライバーの教育事業をネパールにて展開し、依頼に対して迅速な対応ができるように、準備を進めてきました。現在は教育を終えて内定を待っている候補者が多くいるため、圧倒的なスピード感での入国を実現させることが可能となります。ネパール現地では国家資格を有する日本人の教職員を駐在させ、ドライバー教育を行っております。そして今回、1月21日(水)~23日(金)にかけ実際の教育現場の見学や、現地の日本語学校、教習所を視察し面接が可能なツアーを開催することが決定いたしました。今回はその内容についてご紹介します。 -
現地教育
弊社アズスタッフでは、ネパールの現地企業と連携した特定技能ドライバー教育事業の開始を発表しました。2024年3月、特定技能制度に自動車運送業に追加されましたが、現状はまだ広く浸透していないことを背景に、アズスタッフでは、国家資格を有する日本人の教職員を現地に駐在させ、ドライバー教育を行う事業に乗り出しました。今回はその現地での事業の内容をご紹介します。 -
ヨシ! 「仕事猫」が車輪脱輪事故防止を啓発
一般社団法人日本自動車工業会は、人気キャラクター「仕事猫」とコラボし、大型車の車輪脱落事故防止を啓発するチラシを制作しました。本記事では、車輪脱落事故の概要や原因、日常的に行える対策などを紹介していきます。「仕事猫」や、「車輪脱落予兆検知装置」についても解説していくので、ぜひ参考にしてください。