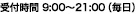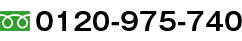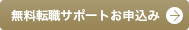HOME > ドライブワーク通信 > 引越事業者優良認定制度(引越安心マーク)とは?概要と取得の手順を紹介
ドライブワーク通信
引越事業者優良認定制度(引越安心マーク)とは?概要と取得の手順を紹介
「消費者に選ばれる引越事業者でありたい」
「引越作業の質の高さをアピールしたい」
引越事業者のなかには、上記のような悩みをお持ちの引越事業者の方もいるのではないでしょうか。
多くの消費者は、できるかぎり信頼のおける引越し業者に依頼したいと考えるものです。
そこで効果的なのが、「引越事業者優良認定制度(引越安心マーク)」の取得です。
全日本トラック協会(全ト協)による認定制度なので、取得すれば客観的に引越作業の質の高さをアピールすることができます。
本記事では、引越安心マークの概要と、取得手順について解説します。
取得を検討している方は、ぜひ参考にしてください 。

インターネットの普及により、消費者は引越の際、多くの選択肢のなかから、自身の予算や都合に合った事業者を選べるようになりました。
しかし、選択肢が増えたことで「どの事業者に依頼すれば良いのか分からない」と悩む消費者も増加していました。さらに「引越し作業の質が低い」「料金が不適切」といった、悪質な事業者によるトラブルも跡を絶ちませんでした。
こうした背景を受け、全ト協は2014年から、引越安心マークを創設しました。
引越安心マークは、全ト協が「優良な事業者である」と認定したことの証明です。そのため、引越安心マークを取得した事業者であれば、消費者は安心して依頼することができます。
もちろん、事業者の目線でも、引越安心マークがあれば、引越業務の質の高さを消費者にアピールでき、集客につながるため、大きなメリットがあるといえるでしょう。
引越安心マークの審査は、以下のスケジュールに沿って進みます。
- ● 説明会:4~6月
- ● 申請書の頒布:説明会開催初日~震災受付日の前日
- ● 申請期間:7月中旬~8月上旬
- ● 審査結果の発表:12月中旬
取得するためには、申請資格を満たし、申請期間中に申請したうえで、審査に合格しなければなりません。
以下では、引越安心マークの申請資格、審査基準、認定の有効期間について、それぞれ説明します。
引越安心マークを申請するためには、以下の2つの条件を満たしている必要があります。
- ● 引越に関わるすべての事業所に、全日本トラック協会の引越管理者講習を、過去3年以内に終了した者が1人以上在籍している
- ● 引越に関わるすべての事業所にが、「Gマーク」を取得、もしくは「安全性優良事業所」相当の認定を受けている
引越安心マークの審査は、以下の7つの基準に従っておこなわれます。
- 1. 引越における約款を遵守している
- 2. 苦情などに適切に対応できる体制の整備と、責任の所在の明確化がされている
- 3. 適切な従業員教育が行われているか
- 4. 引越に関係する法令を遵守しているか
- 5. 廃棄物処理などを適切に行っているか
- 6. 個人情報の取扱いを適切に行っているか
- 7. 制度の信用を損なう行為、もしくは信用を損なう恐れのある行為がないか
引越安心マークは、認定された年度の1月1日から数えて3年間有効です。
以降の更新には、3年毎におこなわれる更新審査で合格する必要があります。
引越安全マークの概要と、取得手順を紹介しました。引越安全マークは、全日本トラック協会による認定を受けている証明になるため、取得していれば依頼を検討している消費者に対して安心感を与えられるでしょう。取得するためには、申請基準と審査基準を満たしたうえで、7月中旬~8月上旬の申請期限中に申請する必要があります。
文/BUY THE WAY lnc.
-
白トラ行為への規制強化 ポイントを解説
2026年4月1日より、貨物自動車運送事業法の改正法が一部施行され、違法な白ナンバートラック(白トラ)への規制が強化されます。従来の白トラ規制は、主に運送を行った事業者が処罰の対象でしたが、この規制強化により、運送を行った荷主も責任を問われることになります。 -
冬用タイヤは「溝深さ」に注意 重要性と確認方法を紹介
冬季のトラック輸送では、路面の凍結や積雪がある地域での走行が避けられず、冬用タイヤの装着が不可欠です。しかし、安全に走行するためには、単に冬用タイヤを履くだけでは不十分で、適切な管理が欠かせません。なかでも特に重要なのが、タイヤの「溝深さ」です。本記事では、大型車の冬用タイヤにおける溝深さの基礎知識や重要性、点検方法などを分かりやすく解説します。ぜひ参考にしてください。 -
1月開催!外国籍ドライバー採用に向けたネパール視察ツアー企画!
2024年3月、特定技能制度に追加された自動車運送業分野。弊社アズスタッフでは先行して特定技能ドライバーの教育事業をネパールにて展開し、依頼に対して迅速な対応ができるように、準備を進めてきました。現在は教育を終えて内定を待っている候補者が多くいるため、圧倒的なスピード感での入国を実現させることが可能となります。ネパール現地では国家資格を有する日本人の教職員を駐在させ、ドライバー教育を行っております。そして今回、1月21日(水)~23日(金)にかけ実際の教育現場の見学や、現地の日本語学校、教習所を視察し面接が可能なツアーを開催することが決定いたしました。今回はその内容についてご紹介します。 -
現地教育
弊社アズスタッフでは、ネパールの現地企業と連携した特定技能ドライバー教育事業の開始を発表しました。2024年3月、特定技能制度に自動車運送業に追加されましたが、現状はまだ広く浸透していないことを背景に、アズスタッフでは、国家資格を有する日本人の教職員を現地に駐在させ、ドライバー教育を行う事業に乗り出しました。今回はその現地での事業の内容をご紹介します。 -
ヨシ! 「仕事猫」が車輪脱輪事故防止を啓発
一般社団法人日本自動車工業会は、人気キャラクター「仕事猫」とコラボし、大型車の車輪脱落事故防止を啓発するチラシを制作しました。本記事では、車輪脱落事故の概要や原因、日常的に行える対策などを紹介していきます。「仕事猫」や、「車輪脱落予兆検知装置」についても解説していくので、ぜひ参考にしてください。