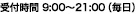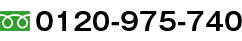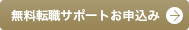HOME > ドライブワーク通信 > 世間のひとびとがトラックドライバーに抱くイメージとは
ドライブワーク通信
世間のひとびとがトラックドライバーに抱くイメージとは
全日本トラック協会では10月9日の「トラックの日」にあわせ「トラック運送に対する意識調査」を実施。
実施期間は2020年9月11日~14日の4日間で、調査対象は全国の20歳~69歳の男女。1000件の有効サンプルを集計しました(調査内容はいずれも全日本トラック協会調べ)。
全回答者に対して「トラック輸送は生活と経済のライフラインだと思いますか?」と質問したところ、「とてもそう思う」が50.8%、「まあそう思う」が39%。あわせると90.2%が「そう思う」と答えました。
「もしもトラックが止まってしまったらどれくらい困ると思いますか?」という質問には、「とても困ると思う」が65.1%、「まあ困ると思う」が27%で、あわせると92.1%が「困ると思う」と回答。
いずれの項目でも、トラック輸送の重要性が広く認知されていると分かる結果になりました。
トラック輸送が担う役割については、世の中のひとびとにどの程度認知されているのでしょうか。
「トラック輸送が止まってしまった場合に起こることが予想される問題について、社会的な影響が大きいと思うものをお選びください」という質問では、「食材が届かず飲食店がお店を開けなくなる」が71%で最多。
他にも「医療用品が病院に届かず治療ができなくなる」が68.1%、「生産者・メーカーからの商品が届かずお店から商品が消える」が67.5%、「ガソリンスタンドにガソリンが届かず車が使えなくなる」が62.2%と、日常生活の根幹にかかわる部分での回答が多くなりました。
一方で、まだ充分に認知されていないトラックの活躍もあることが分かりました。「トラックが国内貨物輸送量の9割を運んでいること」については、「知っていた」が27.3%、「知らなかった」が72.7%という結果に。
「トラックは地震・台風などの災害時に、国や自治体などと連携して被災地に緊急支援物資の輸送をしていることを知っていましたか」という質問では、「知っていた」の割合が52.9%と、約半数のひとに知られていることが分かりました。
日常生活における大型トラックとの関わり方について。
「渋滞中に大型トラックの左側をバイクや時転車ですり抜けることは大変危険なことだと知っていましたか」という質問では、「知っていた」が64.1%。大型トラックは死角が大きいため、左折時に巻き込まれる可能性があります。事実、大型トラック左折時の死亡事故のうち8割以上が自転車の巻き込みとなっています。
「大型トラックの前に急な割り込みをするのは乗用車の前に割り込むより危険なことを知っていましたか」という質問では、「知っていた」の割合が62.0%。大型トラックは乗用車のように簡単には止まれず、追突や荷崩れ、横転してしまうリスクがあります。
いずれも大事故に繋がる項目であるため、6割強という認知度はまだまだ充分ではないとみなすべきでしょう。
「トラックドライバーにはどのようなイメージをお持ちですか」という質問には「力強い・たくましい」が最も多く52.1%。
「荷物を届けてほしいと思うのはどのようなトラックドライバーですかという質問に対しては「荷物の扱いが丁寧」が53%、「礼儀正しい」が46.2%、「気配りができる」が35.2%などの回答が集まりました。
文/BUY THE WAY lnc.
-
白トラ行為への規制強化 ポイントを解説
2026年4月1日より、貨物自動車運送事業法の改正法が一部施行され、違法な白ナンバートラック(白トラ)への規制が強化されます。従来の白トラ規制は、主に運送を行った事業者が処罰の対象でしたが、この規制強化により、運送を行った荷主も責任を問われることになります。 -
冬用タイヤは「溝深さ」に注意 重要性と確認方法を紹介
冬季のトラック輸送では、路面の凍結や積雪がある地域での走行が避けられず、冬用タイヤの装着が不可欠です。しかし、安全に走行するためには、単に冬用タイヤを履くだけでは不十分で、適切な管理が欠かせません。なかでも特に重要なのが、タイヤの「溝深さ」です。本記事では、大型車の冬用タイヤにおける溝深さの基礎知識や重要性、点検方法などを分かりやすく解説します。ぜひ参考にしてください。 -
1月開催!外国籍ドライバー採用に向けたネパール視察ツアー企画!
2024年3月、特定技能制度に追加された自動車運送業分野。弊社アズスタッフでは先行して特定技能ドライバーの教育事業をネパールにて展開し、依頼に対して迅速な対応ができるように、準備を進めてきました。現在は教育を終えて内定を待っている候補者が多くいるため、圧倒的なスピード感での入国を実現させることが可能となります。ネパール現地では国家資格を有する日本人の教職員を駐在させ、ドライバー教育を行っております。そして今回、1月21日(水)~23日(金)にかけ実際の教育現場の見学や、現地の日本語学校、教習所を視察し面接が可能なツアーを開催することが決定いたしました。今回はその内容についてご紹介します。 -
現地教育
弊社アズスタッフでは、ネパールの現地企業と連携した特定技能ドライバー教育事業の開始を発表しました。2024年3月、特定技能制度に自動車運送業に追加されましたが、現状はまだ広く浸透していないことを背景に、アズスタッフでは、国家資格を有する日本人の教職員を現地に駐在させ、ドライバー教育を行う事業に乗り出しました。今回はその現地での事業の内容をご紹介します。 -
ヨシ! 「仕事猫」が車輪脱輪事故防止を啓発
一般社団法人日本自動車工業会は、人気キャラクター「仕事猫」とコラボし、大型車の車輪脱落事故防止を啓発するチラシを制作しました。本記事では、車輪脱落事故の概要や原因、日常的に行える対策などを紹介していきます。「仕事猫」や、「車輪脱落予兆検知装置」についても解説していくので、ぜひ参考にしてください。